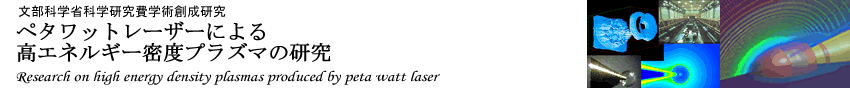
|
No.13 |
| 33rd European Physical Society Conference |
大阪大学レーザーエネルギー学研究センター |
|
6月19日(月)から23日(金)までローマのAngelicum, Pontificia Universita` San Tommaso d’Aquinoにて33rd European Physical Society Conference on Plasma Physicsが開催された。本学術科研からは私とNIFSの坂上先生が参加し、統合シミュレーションの結果について報告した。セッションはMagnetic Confinement Fusion (MCF), Beam Plasmas and Inertial Fusion (BPIF), Dusty and Low Temperature Plasmas (DLTP), Basic Plasmas and Space and Astrophysical Plasmas (BPSAP)の4つからなり、15件のPlenary talkとMCF 495件(454), BPIF 167件(132), DLTP 109件(101), BPSAP 109件(83)の発表があった(カッコ内はposter発表件数)。Oral sessionは室内で5日間、poster sessionは中庭を取り囲む回廊で水曜を除く4日間行われた。 写真1:中庭でのポスターセッションの様子
写真2:Coffee Break ITERの池田機構長ならびに今年のAlfven賞を受賞したPaul-Henri Rebutのスピーチで会議が始まった。BPIFセッションでは、慣性核融合を直接対象としたものよりも高強度レーザーを用いた粒子加速や高速粒子の輸送、アト秒パルス発生、レーザーショックによる高エネルギー密度科学(warm dense matterや状態方程式)等の高強度レーザーに関連した基礎物理・応用の発表が多かったように思う。 粒子加速については高エネルギー化・単色化が精力的に進められている。電子加速では、臨界密度以下のガスジェットターゲットと高強度レーザーの相互作用で生じる“バブル加速”による単色電子ビーム(70MeV ΔE/E〜3%)の発生、さらに対向レーザーを照射することで強制的にバブル内に電子を入射させる方法で、より高エネルギー(~200MeV, ΔE/E〜5%)の電子ビームを再現性よく発生させた実験結果が紹介された。イオン加速についてはTi-foilターゲット上にdot状(0.5mm厚、20×20mm)のpを貼り付けることでビームの単色化に成功した例(実験+シミュレーション)、平板ターゲットの裏面に漏斗を逆向きに取り付けたような”Pizza-cone”によりプロトンをより高エネルギーに加速した例、パラジウム平板ターゲットに数〜1000Å厚の炭素をドープし、ターゲットを〜1,100Kまで加熱することでターゲット中のプロトンを除去した上でレーザーを照射して、炭素を3MeV/u(ΔE/E~17%)まで加速した結果等が報告された。ターゲット裏面のビーム伝播領域にシリンダーを置き、ビーム伝播に同期してこのシリンダーにレーザー照射してシリンダー内にシース電場を形成し、プロトンビームの収束およびエネルギースペクトル調整を行う方法も示された。これらの粒子加速については、今後のレーザー増強・高精度化(各国で計画中・もしくは進行中) により、更なる進展が見込まれる。 慣性核融合に関しては、直接照射、間接照射、Z-pinchでの爆縮実験や解析結果、高速点火における高速電子輸送やコア加熱過程の解析結果等が報告された。Betti(LLE)からはpicket pulseを用いたshaped pulseによるRT成長率抑制法や高速点火を想定したクライオターゲットに対する高密度爆縮のpulse shaping(slow implosion)、その結果得られる爆縮コアに外部加熱を加えて行った燃焼計算に基づく利得評価の報告が行われ、200kJ爆縮レーザー200kJ+加熱レーザー50kJで利得〜100実現の可能性が示された。Honrubia(Madrid工科大) の3D Hybridコードを用いた高速電子によるコア加熱解析では、コアへのエネルギー付与はcollisional processが支配的であること、電子ビームがコアまで伝播する途中にWeibel不安定性によりフィラメント化してコアを非一様に加熱し、局所的には電磁場を無視した場合よりも温度が高くなることが示された。パラメータサーベイにより、ビーム電子のエネルギーが低いほど(1.5MeV程度)コアへの付与エネルギーは大きく、またコーンーコア間距離が離れすぎると加熱が急激に悪くなり、100mm以内が望ましいことが示された。Atzeni(ローマ大)はこれまでの高速点火の点火条件解析をさらに進め、加熱ビームの飛程やビーム半径を考慮したものに改良した結果を報告した。100kJ程度の加熱レーザーで点火させるには高密度爆縮 (300~400g/cm3)が不可欠で、且つ高速電子の飛程が古典的な値より短くなるか、加熱レーザー波長をより短波長にする必要があることを指摘した。これらの実験や解析結果の報告とは異なり、Batani (Milano大)は高速点火の課題を列挙し、実際に高速点火に対するCritical analysisとCritical reviewの必要性を訴えた。LULIで行った平板にコーンをつけたターゲットに高強度レーザーを照射した実験では、コーンによる加熱特性の向上は観測されず、コーンによる加熱効率向上に対して疑問を呈していた。また、“コア加熱の要請(10kJ/10ps local heating)を満たすような電子ビームをコアに入射する事が可能か?”という点では、高強度レーザー照射からコアでのエネルギー付与までの一貫した解析が必要であろう。本学術研究で開発を進めている高速点火統合コードFI3の謳い文句である“爆縮からコア加熱−核融合燃焼までの一貫したシミュレーション”を他に先んじて実現し、激光XII+PWレーザーによる統合実験解析からFIREX、その先の高利得ターゲットまでの解析を行い、コーンターゲットでの高速点火実現の可能性について提示する必要性を強く感じた。 写真3:会議場内にある聖堂 現存の高強度レーザーの増強計画や新プロジェクトに関する報告では、フランスに建設中のLMJ以外に、イギリスRutherford lab.のAstra laserやValucan laserの増強、フランスのLIL(LMJのプロトタイプレーザー)にPWを追加する計画、さらにはヨーロッパ全体として次世代超高強度レーザー装置ELI(Extreme Laser Infrastructure: 350~700PW, >1025W/cm2)や高速点火実験装置HiPER(High Power Experimental Research Facility)の構想が紹介され、各国個別にではなく、高強度レーザー物理ならびに高速点火研究を旗印にヨーロッパ連合として動き始めたようである。これらのnew project報告ではAcademic usageもしくはcivilian laserという言葉が多用され、軍事研究との併用からの脱却が強調されていたように感じた。 最後に雑感を。会議前の日曜とエクスカージョンの水曜午後に街を散策した。ローマの街はさすが2000年の歴史を感じさせ、コロッセオ、コンスタンティヌス帝の凱旋門、フォロ・ロマーノ、パンテオン、サンピエトロ大聖堂等、名高いものだけでなく街中に史跡・建造物がごろごろしており、遺跡の中に街があるといった感じである。35度を越す猛暑の中、ローマ大好きレーザー研A先生のガイドの下、コロッセオとパラティノの丘を見学。当時の建造物がいまだに残っていることとそのスケールに、またA先生のローマ愛と猛暑に圧倒されてしまった。一方、夜はホテル近くのバーでW杯観戦。日本戦を2試合見たのだが結果は皆さんご存知のとおり。ブラジル人サポーターから慰みのビール差し入れを頂く結果となった。 次回EPSはワルシャワ、その後はクレタ島での開催との事です。 写真4. ローマ遺跡 コロッセオ
(NO.13) |



