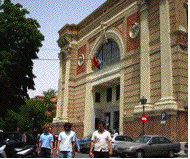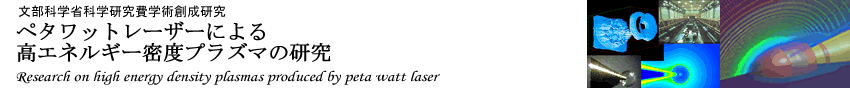
|
No.13 |
| 29th European Conference on Laser Interaction with Matter |
大阪大学レーザーエネルギー学研究センター |
|
去る6月12日(月)から16日(金)までスペイン・マドリッドにて第29回ECLIM(European Conference on Laser Interaction with Matter)が開催された。この国際会議は2年に一度ヨーロッパ内で開催されており、今年はマドリッド工科大学にて行われた。本会議は、その会議名にもあるようにレーザーと物質の相互作用をテーマとしており、慣性核融合を中心に高エネルギーレーザー生成プラズマに関する幅広い研究を対象としている。今回の会議には23ヶ国から約160名の参加者があった。内訳は、アメリカ及びロシアから各34名と最も多く、ヨーロッパ各国から数名ずつ日本からは9名が出席した。口頭発表が117件、ポスター発表が67件であった。本会議のトピックスは、レーザー・プラズマに関する基礎物理から、慣性核融合、高エネルギー粒子加速、プラズマ計測、X線レーザー、ターゲット技術までレーザー・プラズマ相互作用に関する大半の分野をカバーしている。 会議の初日から二日目にかけて、各研究機関のオバービュー発表が行われた。そのいくつかを列記すると、ローレンス・リバモア研の国立点火施設(NIF)、フランスのLaser Mega Joule(LMJ)、ロチェスター大のOMEGA EP、といった大型慣性核融合施設の建設進捗状況の報告から始まり、英国ラザーフォード、サンディアのZピンチとテラワットレーザーを組み合わせたZ-Beamlet、チェコのPALS、ロシアのIskra5、など各研究機関からの最新の研究成果が報告された。その他にも、ここ数年で完成するレーザー実験施設についての発表があった。ドイツGSIではPHELIXを建設中で、レーザーと重イオンビームの同時照射によるwarm dense matter や高エネルギー密度プラズマにおける新しいアプローチについて発表された。ラザフォードではAstra Gemini計画として、二本のペタワットレーザーを用い集光強度1022~1023W/cm2に及ぶ超高強度レーザーの建設が行われており、新しい極限状態の生成そして解明を目指している。その後、高速点火核融合、プラズマ計測、ターゲット技術、X線レーザー等の講演が続いた。昨年のAPS等では電子加速に関する研究が脚光を浴びていたのを思い出すが、今回はわずか1件のみ。かわってイオン加速に関する発表が13件あり、非常に興味深い研究が多かったのが印象的だった。その中のいくつかを紹介したい。 日本原子力機構の大道氏らのグループでは、レーザーの薄膜ターゲット照射により発生したプロトンビームに、その伝播過程でRF電場を印加することで位相空間内でのバンチングを行っている。この位相回転のアイデアを使った単色イオンビーム発生を目指していた。10Hz照射のレーザー装置を用いシングルショットのリアルタイム計測を行っており、再現性が高く非常に精度の高い実験が行われていた。ラザフォード研究所ではプラズマミラーを用いプレパルスとメインパルスのコントラスト比を109~1010まで高めることで1mm以下の超薄膜ターゲット照射の実験を行っている。ターゲット厚の減少に伴い高エネルギー電子の電荷密度が上昇する。その結果、裏面の静電場強度が大きくなりより高エネルギーのイオンを発生させることができる。実験では0.1mm厚のターゲットを用いることでイオンの最大エネルギーが5倍程度上昇させることに成功していた。ドイツFriedrich-Schiller大(Jena)では被加速イオンとして裏面に付着しているイオンを使うのではなく、裏面に貼り付けたプロトン層を用い、それらを選択的に加速することで単色プロトンビームの発生を実現していた。実験結果は2次元粒子シミュレーションにより良く再現されていた。Jenaでは集光強度1021W/cm2のペタワットレーザー(PORALIS)を建設中である。その設計パラメターを用いた粒子シミュレーションでは、最大エネルギー173MeV・エネルギー広がり1パーセントの単色ビームの発生が予想されており、その実現に自信を見せていた。その他にも、レーザー照射した金属管の中にイオンビームを伝播させることで空間的なビームの集束を行うmicro-lensのアイデアも紹介された。興味深いのは空間的集束のみならずエネルギー空間での集束も行われておりビームの単色化が可能であるとのことだった。Max-BornではCPA増幅を2度行うdoubleCPA法によりコントラスト比を高いレベルで制御していた。特に、コントラスト比が108と5×107の場合の薄膜照射実験の比較を発表していた。5×107の場合、ターゲット垂直方向のみ電子及びイオンが観測されるが、コントラスト比が高いと前面でのポンデロモーティブ加速によりターゲットに垂直な方向に加えレーザー照射軸方向にも電子及びイオンが観測されていた。いずれの研究でも現状においては、エネルギー・ビームの質共に医療応用等で求められているレベルまで達していないが、レーザー・イオン加速の実用化に向かって進められており勢いが感じられた。 次回は2年後GSIの主催でドイツ・ダルムシュタットにて開催される予定である。
写真1:会議開催場所
写真2:マドリッドの街角にて (NO.13) |