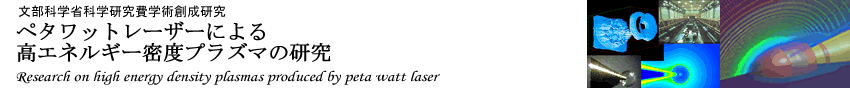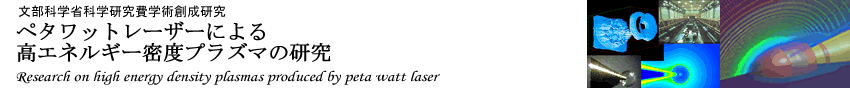|
8月25-27日、San Franciscoの東にあるPleasantonにて短パルスレーザーと物質の相互作用の数値解析に関する国際ワークショップ“Short-Pulse
Laser Matter Computational Workshop”が開催された。PleasantonはSan Franciscoの郊外、Livermoreの近くにある街で、気温は日中30度を越えるものの乾燥しており、街中もごみごみしておらず、快適であった。(会場のエアコンが効きすぎて非常に寒く・・そう感じていたのはNevada大から参加していた千徳さんを含む日本人ぐらいだったようだが・・と、周囲にめぼしい繁華街がなく食事に困った点・・千徳さんと泉さん(Livermore)に誘われ、米国について2日目には日本食を食べたりしたが・・と、を除けばですが。)
さて、本題のWSの報告。
近年のレーザー技術の急速な進展に伴い、レーザープラズマ相互作用が相対論的領域に達し、MeV電子およびイオンの発生が実験で観測され、これら高エネルギー粒子を用いた様々な応用(高速点火核融合・医療・核科学・実験室宇宙物理)が提唱されている。その根本となるレーザーと物質の相互作用、および高エネルギー粒子の発生輸送過程の物理機構の解明は理論・シミュレーションにより精力的に進められているが、個々の物理現象の解明や、実験を再現するようなオーバーオールな解析を行うには至っていない。これは、解析手法によって考慮できる現象や空間・時間スケールが異なり、ミクロスケールで生じる物理現象とマクロスケールで生じる現象とを自己無撞着に全体を通したシミュレーションが、困難なためである。
そこで、本WSは、高強度短パルスレーザーと物質の相互作用から相対論的電子輸送やイオンビーム発生を対象に、異なるコード間での解析結果の比較や、オーバーオールな解析の方法、またコード比較を目的とした解析対象の設定等を目的として開催された。参加者の大半を米国研究者が占め、他国からは英国から1名、仏国から1名、および日本からは私と坂上氏(兵庫県立大)の2名が参加した。
会議自体は最初に数件のレビュー講演が行われた後、個々のテーマに基づいた個別セッションが行われた。個別セッションの運営はチェアマンに任せられ、予め設定された課題に基づいて適当に発表者を募り、その内容に基づいて議論を発展させていく方式で行われた。いわゆる学会での10分程度の発表+数分の議論といった形式ばったものでなく、とことん議論するというやり方で、深い議論ができた。
内容としては、レーザープラズマ相互作用、高速電子輸送、異常抵抗、イオン輸送、阻止能、Kα計測と様々な議論がなされたが、終盤は粒子コードグループとHybridグループの議論に集約し、一部LSP(Laser
Scale Plasma Simulation Code:Mission Research Corporation 社製)ユーザ会のような雰囲気が有り,LSPユーザにしかわからない方言が飛び交って議論が行われていた。実際、アメリカではLSPユーザ数がかなり多くなっているようだ。また、共通課題を設定して互いの結果を比較検討しようという雰囲気に盛り上がりかけたが,具体的な課題の設定までには至らなかった。また、オーバーオールな解析の方向性としては、(A)レーザープラズマ相互作用から高速電子およびイオンの伝播までの全過程を粒子コードで行う、もしくは(B)複数のコードを結合(例えばレーザープラズマ相互作用は粒子コード、伝播過程はLSPのようなHybrid)して行うという2パターンの方向性が示されていたが、さすがに粒子コードで全体をカバーするのは困難なようで、複数種のコードを結合して解析する方にあるようであった。統合コードプロジェクト"FI3"を掲げている我々としては、うかうかしていられない状況となっている。

Desert City RENOの夜明け
会議の発表資料の一部をレーザー研内部向けのHPで公開しておりますので、興味のある方はご参照ください。(http://133.1.154.233/tulu/2004Pleasanton)
WS終了後、Nevadaに移り、Nevada大RENO校のNTF(Nevada Terawatt Facility)を訪問(8/31)し、千徳さん、Ruhlさんと共にコーンターゲットを対象とした解析内容や今後の方向性等について議論をした。(NTFについては学術創成HPのNewsLetter(http://www.ile.osaka-u.ac.jp/gakujutsu/HomePage/news%20letter/PetawattersNo3.pdf)に千徳さんからの紹介記事があるのでご参照ください。)
Renoは標高1000mの砂漠の中に水を引いて作った街で、Pleasanton以上に日射しはきつく暑かった。よくこんなところに街を作ったものだと思う。緑と言えば、人々が木々を植えて日夜水をやっているところだけで、庭の外は砂漠・・・・といった非常に厳しい環境である。しかし、近年、多くの企業がSan
Franciscoから税金の安いRENOに移転してきているようで、急速に街が広がっていっているそうだ。ちょっとしたバブル景気となっているとのこと。一方で、近々深刻な水不足になるだろうとの予測も。
最後に、今回は坂上先生(兵県大)との2人旅で、常に行動を共にしていた。ここでは特記しないが、色々な点で坂上先生のタフさに非常に感動した。(その後の青森物理学会で再認識することになったが・・・。)最終日、さすがに私は疲れきっていたようで(前夜のタイ料理でおなかを壊し、夜寝られなかったのも要因ではあるが)、朝起きられず、坂上先生にわざわざ部屋まで起こしに来てもらった・・・結果、朝食を奢る羽目となったが無事飛行機には間に合うことができた。坂上先生、どうもありがとうございました。
(No.7) |