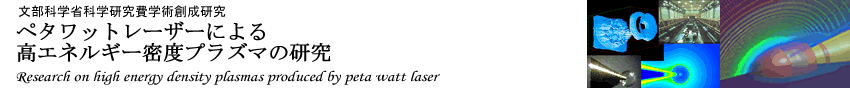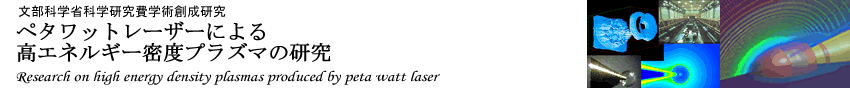|
本センターでは、ガラス細管(キャピラリー)を用いたレーザー加速実験で、世界で初めて、電子を1億ボルトにまで加速した。Physical
Review Letters 最新号(vol.92, N0.20 (2004))に掲載。
レーザーは集光すると、その分発散するという宿命がつきまとう。レーザー加速を田島俊樹氏らが提唱したその当初から、実用に十分な加速長を得るためには、ファイバイーガイドが必要とされていた。レーザーの発散を抑え、レーザー、プラズマ波、加速粒子の3者の位相がずれないようにするためである。そういうわけで、ファイバー加速、或いはキャピラリー(細管)加速の研究が世界中で行われている。その中で阪大が、キャピラリー加速に成功した。鍵は、キャピラリーの内径にある。レーザーのスポット径の数倍がよいと見出したことであろう、大きすぎては、レーザービームが中で踊り回る。小さすぎては、中に生成されるプラズマ密度があがりすぎる。但し、数倍の内径では、ほとんどレーザー光を導入することはできない。内径数十ミクロン、長さ数cmのガラスキャピラリーの先端に1mmの金の漏斗をつけ、レーザー光を効率よくキャピラリーに導入するというナノ技術が成功の鍵でもある。高速点火で培われた技術の移転である。
実験結果が航跡場の1および2次元PICシミュレーションの結果と、奇妙にもよくあう。シミュレーションの結果では、自己収束など、超高強度場と言う言葉から危惧される様な不安定性が観測されない。トムカツオレアス博士の言葉にもあるように、不安定性の心配がなくなるなら、キャピラリー加速の実用化へのメリッもさることながら、大人しくなることへの物理的興味も、大きなメリットと言えよう。超高強度場の面白い振舞いの一つかもしれない。
フィジカルレビューレター査読射2人のコメントの一部:
「キャピラリーというものが初めて電子を加速したという興奮を禁じ得ない、先進加速器研究分野のみならず、広く高エネルギー物理学の世界にとって興味が尽きない。」
「キャピラリー加速の実験的検証として非常に重要で、数多く興味深い検証を含んでいて、加速器物理の基礎をなす重要な結果である。専門を超えて広く興味がもたれる。」
米国物理学会推薦者南カリフォルニア大教授トムカツオレアス博士のことば:
「壮観である。阪大はレーザー加速の聖杯holy-grail を勝ち取った。しかもmmを越える短パルスレーザーのチャンネルを作ったのである。今までの世界中のすばらしい仕事と比較できるものである。不安定性の心配のない制御されたレーザー加速の将来が約束される。」
(No.6)
|